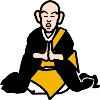|
|
|
|
|
|
||
|
「あいさあいべ!」とは「会いに行きましょう!」という意味の米沢弁です |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続公の生涯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長7年 1602年 43歳 〜 慶長14年 1609年 50歳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長 7 |
1602 |
43 |
兼続>直江兼続公、実の父 樋口惣右衛門兼豊公が米沢で亡くなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
兼続>亀岡文殊堂にて詩歌会を催す。この時詠まれた詩歌は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「文殊堂詩歌百首」として現在も亀岡文殊堂「大聖寺」に所蔵されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>直江兼続公、「藩政改革」と「米沢城下の街づくり」に着手。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
実際はこの後次々と幕府から土木工事を課せられ、本格的な街づくりは |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長13年1608年、直江兼続公49歳の時からになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
この頃の書籍ではないかとして「四季農戒書」という本が遺されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
正式名:「地下人(百姓のこと)上下共身持之書」。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
働く喜び、生きる喜び、工夫、栽培方法、食べ方等が細かく記述されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直江兼続公の執筆と考えられて来ましたが、昨今の研究で元禄期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1688年〜1703年)の作との見方が強まり、直江兼続公説、更に直江家に |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
婿養子として迎えられていた本多正信の次男政重が、常々直江兼続公から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聞き及んだことを一冊の本にまとめたという本多政重説も年代の違いから |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
否定されつつあります。現在は誰かが直江兼続公の没後に名前を借りて |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
書いたのではないかという説が有力になって来ています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長 8 |
1603 |
44 |
日本>2月9日、徳川家康、京都伏見城にて右大臣征夷大将軍に任命される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本>2月12日、徳川家康、江戸に幕府を開く。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江戸幕府誕生 |
以来慶応3年1867年10月14日までの264年間、徳川政権が続くことになる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本>徳川秀忠の長女千姫(7歳)豊臣秀頼と結婚。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>上杉景勝公、徳川と豊臣の婚儀のため京都に入る。正室菊姫(大儀院)と再会。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>この冬、上杉景勝公の正室菊姫(大儀院)、体調を崩し床に伏す。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長 9 |
1604 |
45 |
景勝>正月、上杉景勝公、米沢の武田信清(菊姫の義理の弟)を京都伏見に呼ぶ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>2月16日、上杉景勝公の正室菊姫(大儀院)が亡くなる。享年41歳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
菊姫(大儀院)没 |
菊姫は武田信玄の姫として生まれ、上杉景勝公に嫁いでからは京都伏見の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上杉屋敷に入り、以後一度も京都を出ることはなかった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「甲州御前」として上杉の家臣達からとても慕われ、「上杉家御年譜」(国宝)には、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
悲報を聞いた家臣達の様子として「諸士に至るまで悲歎(ひたん)カキリナシ」と |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
記述されている。直江兼続公が交流を持った南化玄興の寺である京都妙心寺に |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埋葬され、米沢の林泉寺には墓碑が建てられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南化玄興没 |
兼続>直江兼続公の学問の師、京都五山 妙心寺の南化玄興和尚が亡くなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
景勝>5月、上杉景勝公側室桂岩院、米沢城にて嫡男を出産。後の二代藩主上杉定勝。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>8月17日、上杉景勝公側室桂岩院、米沢城にて急死。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
桂岩院は家臣達の間であまり評判が良くなかったと言われ、急死は菊姫の祟りだ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とする噂が飛び交った。当初は米沢の林泉寺に埋葬されたが、後に米沢城下の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
極楽寺に改葬されている。以後極楽寺は上杉家側室の菩提寺となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>8月22日、上杉景勝公、京都伏見の上杉屋敷を出発し米沢に向かう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>直江兼続公、江戸幕府の老中本多正信の次男政重を婿養子として迎える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長女於松と結婚、政重は「直江山城守勝吉」と名乗る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鉄砲製造開始 |
兼続>直江兼続公、関西から鉄砲鍛冶職人を招き白布高湯にて鉄砲製造を始める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
米沢南部の山奥で人目に触れること無く極秘に行われた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長10 |
1605 |
46 |
日本>徳川家康、征夷大将軍の職を三男徳川秀忠に譲る。駿府にて大御所政治。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長11 |
1606 |
47 |
兼続>1月、直江兼続公、次女が病気で亡くなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>5月、上杉景勝公、幕府から江戸屋敷を賜る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>8月、直江兼続公、長女於松が病気で亡くなる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
その後、直江兼続公は、実の弟大国実頼の娘を養女として迎え勝吉と再婚させる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>上杉景勝公、幕府から江戸城石垣工事を命じられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長12 |
1607 |
48 |
兼続>直江兼続公、京都の日蓮本宗本山要法寺の僧「日性(円智)」の協力で |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本初となる銅活字印刷本「直江版文選」を刊行する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直江版文選 |
「文選」とは中国の南北朝時代(439年〜589年)に南朝梁の昭明太子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(501年〜531年)によって編集された書物で、周の時代〜梁の時代までの優れた |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文や詩と論文を集め30巻で刊行された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「直江版文選」は中国の宋の時代の「五臣注文選」(1158年)に「李善注文選」を |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加え編集され刊行された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長13 |
1608 |
49 |
兼続>直江兼続公、米沢城入城10年目の節目に名前を 「重 光」 と改名する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※当ホームページでは以後も 「直江兼続」 のままで表記いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
米沢城下の街づくり |
景勝>上杉景勝公、直江兼続公に米沢城の大改修と街づくりを命じる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>直江兼続公、米沢城下東側と南側に堀を掘る。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慶長14 |
1609 |
50 |
日本>徳川家康の十一男頼房、水戸徳川家初代藩主となる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景勝>上杉景勝公、幕府から常州常陸国(茨城県水戸)の舟入工事を命じられる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
米沢にて仙桃院没 |
景勝>2月15日、上杉景勝公実母仙桃院(上杉謙信公の実姉)亡くなる。享年82歳。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
景勝>上杉景勝公、老中本多正信の取り成しにより10万石分役儀を免除される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>直江兼続公の長男景明(15歳)、近江国膳所城主戸田氏鉄の娘と結婚。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
媒酌人は老中本多正信。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
戸田氏鉄は、徳川家康の元近習で近江(滋賀県)、摂津(大阪府)と城主を務め |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最後は美濃(岐阜県)大垣城主となる。大垣城跡には銅像が立つ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼続>直江兼続公、米沢城下各所にて宅地の区画整理、田畑整理、治水工事を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現在表示されているページは 「 兼続公の生涯 」 です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2007-2014 上杉時代館. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||