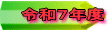
12月11日(木)第2回学校運営協議会の開催
今日の4時間目、委員の方々に校内を一巡していただいた後、4年生の総合的な学習「大塚のにぎわいを取り戻せ」の授業に参加していただきました。子どもたちの考えたプロジェクトへのアドバイス、大変ありがとうございました。その後、給食を試食していただき、最後に1時間ほど学校運営に関わる協議を行っていただきました。本日の資料は、後日、議事録と共にホームページにのせますので、ぜひご覧いただき、ご意見等ありましたら学校までお知らせいただきたいと思います。
 |
 |
 |
11月11日(火)租税教育 感謝状を受賞
今日の午後、米沢税務署長 野崎博行 様、総務課長 佐々木義孝様が来校されました。本校の租税教育推進に係る取組みに対し、野崎様より感謝状と記念品をいただきました。これは、本校が長年にわたり、租税の役割や国民の納税の義務について小さいうちから学ばせるために、租税教室の実施・税に関する絵はがきコンクールへの積極的参加が認められたものであります。感謝状が贈られたのは、管内の小・中・高校の中で1校だけということでした。大変貴重な表彰であり、良き伝統としてこれからも続けていきたいと思います。誠にありがとうございました。
 |
 |
 |
10月19日(日)大塚地区秋の資源回収
朝、7時前には各地区から運ばれたダンボールや新聞紙、雑誌や空き瓶をのせたトラックが並びました。役員だけでなく中学生の協力を得て、安全に、またスムーズに実施することができました。収益金の一部は、来年迎える創立130周年記念事業の予算にあてさせていただくことになっています。小中学生がいない地区も出始めていますが、地域の皆様の協力のもと、地域で学校を支える大塚地区ならではの事業となっています。
 |
 |
 |
10月14日(火)川西町立小学校の適正配置に関する懇談会
| 午後7時より、本校保護者を対象とした標記懇談会が開催されました。片倉教育長、前山教育文化課長、金子課長補佐より、「協議会の設置と今後のスケジュール」「町内小学校の現状」「川西町立小学校の適正配置に関する基本的な考え方と方向性についてご説明いただきました。 昨年度の川西町における出生者数は37名。「子どもの学習や生活の場としての学校本来の機能を優先する」「町における限りあるリソース(資源)を効果的に活用することで小学校の機能を高めていく」という基本的な考え方のもと、将来的には町内小学校1校にすることを目標とする中において、おおむね10年以内に町内5校の小学校を1校ないし2校の配置となるよう検討を進めることを目指しているとのことでした。 11月中には、町内7地区を対象に7会場において懇談会が予定されています。大塚地区は11月5日(水)午後7時から交流センターで開催されますので、ぜひ、ご参加ください。 |
 |
10月 8日(水)就学時健診
| 来年入学する子どもたちや保護者の方に学校においでいただきました。犬川小さんへの入学予定の皆さんも一緒です。 本校には男子7名、女子9名、計16名、犬川小さんには男子5名、女子5名、計10名が入学となる予定です。園児が健診を受けている間に、保護者の方には家庭教育アドバイザーの小松先生の話を聞いていただきました。 うなずきながら聞き入り、話の中にどんどん引き込まれていく、お父さん、お母さん。集まった感想用紙には、「講師の先生の体験談も交えての内容だったので大変参考になった」「普段の親子関係を見直すいいきっかけになった」と保護者の方々にも大変喜んでいただけたようでした。 小松先生大変ありがとうございました。 |
 |
9月20日(土)PTA早朝作業
今年2回目となるPTA環境整備作業を行いました。1~5年生の保護者に加え、5年生も一緒に参加してもらいました。6年生は並行して学年行事を行う予定でしたが、雨のため延期となったため、作業を手伝ってくださった保護者の方や児童もいたようです。整理整頓されたきれいな校舎は子どもたちの健やかな成長にかかせないものです。とてもきれいにしていただき、ありがとうございました。
 |
 |
 |
9月19日(金)ユズリハの伐採
学校に2本のユズリハがありました。調べてみると、平成9年、大塚小PTA設立50周年を祝い植樹されたようでした。何本かは根付かなかったものの、この2本だけは30年近く子どもたちの様子を見守ってくれていました。夏休み明けごろからか、片方の木の葉が全てしおれ、部分部分の葉が枯れたように茶色になりました。樹木医の丸山久先生に見ていただいたところ、根の枯れがひどく、残念ながら治療はきかないとのことでした。根元の揺れもひどいので、歴代PTA会長会の大沼会長にも見ていただき、子どもたちの安全のために伐採することにしました。
いつも敷地内の樹木の困りごとをお願いしている金子美明氏にお願いして切っていただきました。毎年、ユズリハの剪定をしてくださる船山昭司氏も心配してかけつけてくださいました。あと1本となった記念樹ユズリハ。これからのことをPTAで話してみたいと思っています。
 |
 |
 |
8月23日(金)めがね山も喜んでいます
めがね山にある滑り台。だいぶ古くなり、錆がたくさんついていました。来年創立130周年を迎えるお祝いに、何とかきれいにしたいものだと考えていたところ、大塚地区の那須板金さん(那須敏夫さん)がひと肌ぬいでくださいました。子どもたちのいない夏休み中に、滑り台の錆を落とし、錆止めまで塗ってくださいました。本当にありがたかったです。子どもたちは、暑さも気にせず、ピカピカになった滑り台にまっしぐら。喜んで滑り降りてきます。9月には6年生がPTA学年行事で滑り台をペイントします。当日も那須さんが指導に来てくださる予定です。待ち遠しいかぎりです。
 |
 |
7月14日(月)地区高齢者宅訪問花いっぱい運動
おとといの土曜日、大塚地区教育福祉部会が主催する高齢者宅訪問花いっぱい運動が開催されました。大塚小学校6年生にボランティアを募って行うこの活動にたくさんの子どもたちが参加しました。はじめに訪問先の方へメッセージを書きました。完成したグループから、お花を持って民生委員児童委員など役員の方と一緒に訪問者宅に向かいました。帰ってきた子どもたち一人一人の感想発表を聞くと、「考えた質問以外のこともたくさん聞けて良かった」「緊張したけど思ったより上手にできた」ととてもよい体験となったようです。高齢者は地域の宝。これからも、つながりを大事にしていきたいものです。
 |
 |
 |
5月20日(火)生活・総合学習会
昨日、米沢市立南原小学校長(小学校学習指導要領解説の専門的作業等協力者)である高野 浩男 氏を講師に迎え、生活科と総合的な学習の勉強会を行いました。せっかくの機会だったので町内の小中学校に案内したところ、13名の先生の参加がありました。「生活科・総合的な学習の時間で、今、確認したいこと」をテーマにご講話いただきましたが、授業づくりのポイントや教科横断的な視点等、改めてその大切さを振り返る1時間となりました。様々な場において、「今年度の大塚小は生活・総合に力を入れていく」と保護者の方々にお話していますが、そのためにも、教材研究の時間と子どもを真にリスペクトした関わりのできる資質・能力を磨くことに力を入れて進めていきたいと思います。
 |
 |
 |
5月19日(日)春の資源回収
今年もまた、大塚地区春の資源回収が実施されました。大塚地区教育後援会の事業の一つであり、集められた資源の全てを小学校へ寄付していただいているありがたい事業です。7時から始まる作業ではありますが、地区内から集められた資源をのせたトラックは6時過ぎると並び始めます。本当に頭が下がります。また、大塚地区の中学生も作業のお手伝いに集まります。なつかしい子どもたちの顔を見ながら、あんな重いものも持てるようになったのだと大人になった子どもたちにも驚かされます。子どもたちには「地域を愛する心」と「ボランティアの精神」をいつまでも大切にしてほしいと伝えました。地区の皆様、ご協力誠にありがとうございました。秋の資源回収もよろしくお願いいたします。
 |
 |
 |
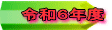
11月22日(金)学校経営計画指導訪問
置賜事務所長 目黒孝博様、川西町教育長 小林英喜様をはじめ多数の先生方に来校いただき、学校の様子を見ていただきました。主任指導主事の多勢千鶴子先生から、各クラスの授業について次のようにお褒めの言葉をいただきました。
1年生 これまでに経験した学び方を使って学べている。
2年生 内容でつないだカリキュラムマネジメントがなされた授業
3年生 子どもたちの声をしっかり拾い上げようとする姿勢が感じられた
4年生 ネクストギガといえる授業づくりだった
5年生 教師が個々の学びをしっかりとつなぎ、子どもたちが安心して授業に参加できている
6年生 知的好奇心の高さが感じられる授業だった 中学校へむけて楽しみ
特支 場所は別でも お互いを感じられる授業だった 涙がでた
伝え合う力のイメージをしっかりと共有し、よりよい学校経営にあたっていきたいと思います。誠にありがとうございました。
 |
 |
 |
10月20日(日)秋の資源回収
朝7時から大塚地区の資源回収が行われました。各地区からライスセンターに運ばれてくる新聞や雑誌、段ボール、瓶やバッテリーはものすごい量になります。資源と時間、労力を費やしていただいた収益金は学校に助成いただいていているわけですが、改めて頭が下がる思いです。有効に活用させていただきます。役員の皆様はじめ地域の皆様、作業を手伝ってくれた中学生に心からお礼申し上げます。また、来年の資源回収へのご協力を宜しくお願いいたします。
 |
 |
 |
6月19日(水)幼保小連絡協議会①
2校時目に、北斗幼稚園より長谷川園長先生はじめ3名の先生に来ていただきました。1年生の頑張っている様子を見て、安心していただけたようです。話し合いでは、幼稚園でも昨年度より縦割り活動に取り組んでいることや自信を持って話ができるように支援していることなど、小学校と共通する点が多くありました。コロナ禍にありなかなか実施できなかった子ども同士・職員間での幼小交流について、今年度は増やしていくことを確認し合ったところです。
 |
 |
 |
6月13日(木)不審者対応訓練
「校内に不審者が侵入した!」侵入の様子や不審者に対峙する様子を、チームズを使ってリアルタイムで子どもに見せながら、子どもも参加しての訓練を行いました。体育館に逃げた後は、子どもたちに声掛け事案の対応法について教えていただきました。
子どもたちが下校した後は、職員だけでの研修会です。上手くいかなかったところは改善し、安全で安心な学校づくりに努めていきます。置賜教育事務所の山口先生、総括少年補導専門官の安達先生、犬川駐在所の小野巡査長さん、お忙しいところご指導いただき、誠にありがとうございました。
 |
 |
 |
 |
6月12日(水)第1回校内授業研究会
置賜教育事務所より、多勢主任指導主事、船山指導主事、川西町教育委員会より、島貫指導主事、佐野指導主事をお招きし、今年度初めての授業研究会を実施しました。今年度の研究テーマは「一人一人がよく学び、互いに高め合う子どもの育成~考えを伝え合う交流を通して~」とし、2つのめざす子どもの姿に迫ります。意見が飛び交う事後研。意欲的に研究に取り組む職員の姿はまさに、子どもたちに求める姿でした。
 |
 |
 |
6月11日(火)心肺蘇生法AED操作研修会
毎年、万が一の事故に備え、校内において伝達研修会を実施しています。今年度はプールサイドで、職員も指導者役、子ども役になり、対応マニュアルを確認しました。1学期だけのプール開放となりますが、一人ひとりのめあてに向かって、事故なく安全に精一杯チャレンジさせたいと思います。
 |
 |
5月19日(日)春の資源回収
晴天の下、事故や怪我もなく、無事、春の資源回収が終了しました。地区の皆様のご協力誠にありがとうございました。
例年同様、中学生にも協力をいただいたことで、作業もスムーズに進みました。大変助かりました。
収益金の一部は、令和8年度に向かえる、創立130周年記念式典の事業費として、少しでも積み立てていきたいと考えています。
大変なことと思いますが、また、秋の資源回収に向けて、新聞、雑誌、空き瓶など保管しておいていただけますようご協力をお願いいたします。
 |
 |
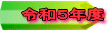
体験楽習(たいけんがくしゅう)楽しい勉強
ご協力いただいた各講座の先生方、たいへんありがとうございました。地域の先生方のおかげで、とても貴重な経験ができました。第127回目の創立記念日に花を添えていただきました。
写真は、上段から
料理教室・かざり作り・紙飛行機飛ばし
プログラミング学習・フラワーアレンジメント・理科実験
グランドゴルフ・リサイクル工作・木工作
茶道体験・ヴァイオリン体験・モルック体験
の全12講座の様子です。
令和5年度 創立127周年記念式 式辞 から
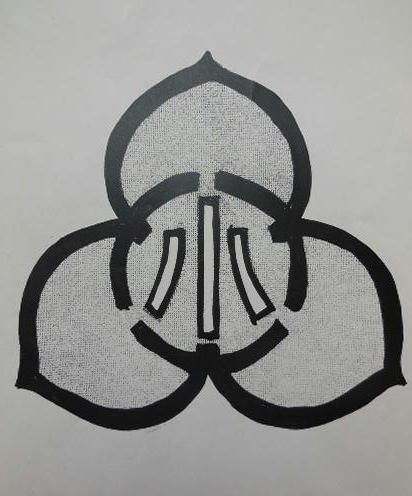
今日は、大塚小学校が始まって127回めのお祝いの日です。そしてこの創立記念式は、みんなで学校の誕生日をお祝いをする式です。
さて、今日は皆さんに、学校の校章のお話をしたいと思います。体育館ステージの一番上に飾ってあるこのマークが、学校のマークいわゆる校章です。創立60周年記念の時に作ったとのことですから、今から67年前の1956年(昭和31年)に作られたものです。
実はその前年の昭和30年に、町村合併(近くの町が一緒になる)があり東大塚・中大塚・西大塚の3つの大塚地区が一つになるという大きな出来事があったのでした。
そこでこの校章をよく見てください。このマークには大塚の「大」の漢字が3つ組み合わされています。この意味は、3つの大塚の地区が一緒になるという意味と、みんながいつまでも仲良く過ごしてほしいという願いが込められているのだそうです。たしかに、大きいという漢字が手をつないでいるように見えます。
さて、そこで問題です。大塚小学校の隣の北斗幼稚園の校章や、当時の大塚中学校の校章はどんな形でしたでしょう。実は、大塚小学校ととても似ている形をしているのです。 つまり、大塚の地域の皆さんは、幼稚園でも小学校でも中学校でも、仲良くしていくことがとても大切ですという考え方や願いを持っていることがわかります。
今日はこのあと体験楽習が実施されます。1年生から6年生までが学年を越えて、そして地域の方をお招きして一緒に勉強する時間になります。ぜひ、学校のマーク(校章)に込められた思いを大切にしてこれからの活動に取り組んでみてください。そして、これからもずっと、思いやりの心を持ってみんな仲の良い大塚小学校を作っていってほしいと思います。頑張っていきましょう。
今日は大塚小学校の誕生日に合わせて、学校のマーク校章のお話をしました。
| 5月2日(火)ヤマザワ川西メディカルタウン店のオープンに伴い、教育振興の目的で、公益財団法人ヤマザワ教育振興基金様から、ジェットヒーター3台と児童用の楽器セット、総額100万円相当の教育機器・教材をご寄贈いただきました。大事に使わせていただきます。ありがとうございました。 |
 |
 |
