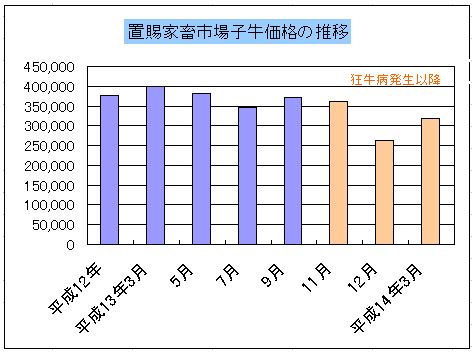2002. May 狂牛病から6ヶ月!
昨年9月10日、国内で初めてBSE(牛海綿状脳症)いわゆる狂牛病が発見されてから、もう半年が経過しました。この間、発生原因の特定がされないまま、現在(2002.4.1)に至っています。しかも、最初千葉県で発見された後、北海道や、群馬県でもBSEが確認され、牛肉の消費は激減し、牛の取引価格も数十年以来の超安値となってしまいました。
また、BSE検査体制がとられ安全な牛肉が市場に出荷されるようなった反面、雪印食品で未検査牛肉の政府買上げ制度を悪用して、外国産の安い輸入牛肉を国産牛肉に偽装し補償金を詐欺した事が判明しました。しかも、その後あちこちの食肉流通業者が牛肉に留まらず、すべての食肉で、産地偽装、ラベルの張り替えなどの不正が行われていたことが発覚し、牛肉に対する消費者の不信感をますます深める事となりました。国政に於いても、農林省の対応のまずさが問われ、農林大臣の辞任が追求されております。
この6ヶ月間、牛肉にとってはまさに異常といえる状態で、われわれ生産者(黒毛和牛飼育者である私の場合)にとっても激動の時でありました。そこで、この半年間の動向がどんなものであったのか振り返って検証してみました。
2001.9.14〜 飼育牛の検査と飼料の調査 と 肉牛出荷の制限
9月10日 千葉県白井市で狂牛病が発見され、農林省を中心にBSE対策本部が設置されて、直ちに日本国中に飼育されている全頭数の牛体検査と、原因と言われる肉骨粉の飼料給与について調査が入る。調査員は家畜保健所の獣医師、県支庁職員、町畜産担当職員。
あわせて30ヶ月以上の肉牛のと畜(出荷)停止措置される。(BSE原体の異常プリオンが30ヶ月未満だとほとんど蓄積がないと言われるためBSE検査体制が整うまでの暫定措置)
| 調査に来た獣医師の談 BSEって不自然な歩き方したり大きな音や光に異常な反応を示すって言うけど、一度も患牛を診察したことがないからなぁ〜……。 |
2001.10.6 JA肉用牛部会のBSE対策本格化
10月に入り全国的な肉牛、子牛の価格暴落に対して、JA肉用牛部会のBSE対策が本確的に動き出す。飼料の原料の明示、出荷制限解除、学校給食などの牛肉使用禁止の早期解除、価格暴落による飼育農家の支援などの要請。
2001.10.18 BSE検査開始
と場でのBSE検査体制が整い、エライザ法による全頭検査されて陰性のみ出荷される事になった。しかし同日、東京芝浦と場で陽性反応の牛が見つかり大騒ぎとなる。検査方法が敏感に反応を示すため2〜3%の割合で陽性反応が出るとの事。2日後2次3次の検査で陰性と判明。
2001.10 〜 肥育牛・子牛価格暴落
スーパーや、小売店では、牛肉が殆ど売れないという事態になり、有名焼肉店も倒産が相次ぎ、肉牛相場が激落となる。枝肉価格がkg当り5円とか10円なんてものも出る事態!(平均枝肉重400kgとすると牛一頭2,000〜4,000円ということになる)
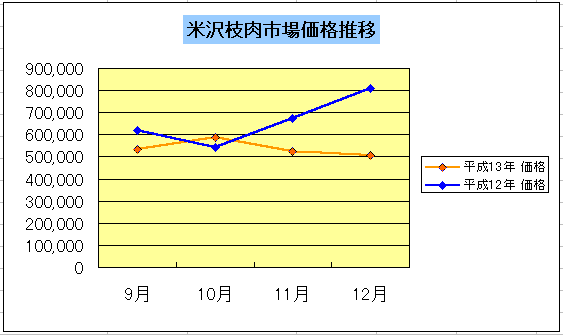 |
|
|
|
2002.1.23 〜 雪印食品牛肉偽装表示発覚
雪印食品は、狂牛病未検査牛肉買取り制度を悪用して、輸入牛肉を国産と偽り国に買取らせていたことが発覚し、国産と輸入の価格差2億円を詐欺した疑いで告発、農林省の立ち入り検査を受け、倒産に至る。その後スターゼン、丸紅畜産など、多くの肉卸問屋の不正表示が次々と明るみになり、牛肉だけでなく、豚、鶏も含めて食品全体の重大問題となる。
おりしも、昨年よりPL法(Product Liabilityの略、製造物責任法 )が制定され、食品に於いても産地等の表示を故意に偽った場合は罰せられるようになりましたが、その刑はまだ軽過ぎます。例えば、不正表示が発覚し注意を受けて表示を適正に直せば会社名などは公表されない。
しかし、一連の狂牛病発生から半年、風評被害からの牛肉消費低迷で、一時は国内の牛肉産業は壊滅状態になるのではと心配されましたが、一流企業が牛肉の産地偽装やレッテルの張替を日常茶飯事にやっていたことが発覚して、日本企業のメチャクチャなやり方に消費者の反感を浴びせられる事となった。儲け至上主義の企業のあり方が改めて見直されるのは当然で、私たち生産者の作った物が正当な表示と価格で消費者の手に渡るよう、つまり、流通の正常化が論議されるきっかけになった事は大きな収獲である。今後とも流通、表示、のルール作りと、遵守に目を配らせて行かなくてはなりません。
2002.2.19 〜 BSE緊急対策個体識別システム事業
 産れたばかりの子牛にも両耳に |
今回のBSE発生で、発病ルートがまだ解明されてないのだが、牛の移動状況が複雑なため、伝染病等の発生時に瞬時に移動経路が解明されるよう、全国統一の個体識別管理システムが発足し、耳標(耳に付ける番号札)を装着する事になった。 以前にも、和牛では、子牛価格安定基金制度加入の証として耳標は付けられていたが、番号が8桁から10桁になり、産れたばかりの子牛にも4枚もの耳標が付けられる事になった。人間の若者の世界では耳ばかりでなく、唇や鼻、等にも穴を明けて喜んでイヤリングを付けるのだが、牛はやっぱりイヤらしい。 BSE騒動で一番の被害者はどうも牛本人だったみたいです。 |